
遮熱と断熱の違いはなに?
と疑問に思ったことはありませんか?
暑さや寒さを防ぐ方法としてよく耳にするこの2つ、実は働き方も使いどころもまったく違います。
そこで、住宅やオフィスはもちろん、工場・倉庫といった法人施設までを視野に入れ、遮熱と断熱の違いを解説。
をわかりやすくご紹介します。
これを読めば、自分に合った対策がきっと見つかりますよ。
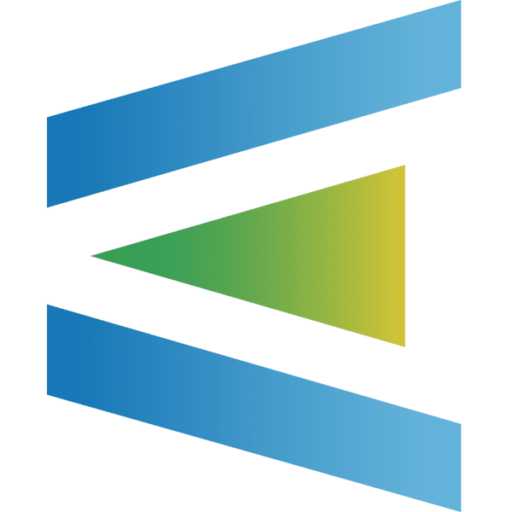
執筆者
株式会社エビスは「遮熱・断熱のソリューション企業」です。これまで遮熱シート『COOL FACE』を用いて、工場・倉庫などの現場課題に向き合ってきました。その実務経験をもとに執筆しています。
目次

「遮熱」と「断熱」。どちらも「暑さ・寒さを防ぐもの」というイメージを持っている方が多いと思います。
しかし実際には、その働き方も、使いどころも、効果もまったく異なります。
最初にこの章では、ふたつの基本的な違いを、わかりやすく解説します。なぜなら、この知識は、住宅選びやリフォーム、エコ対策など、あらゆる場面で知っておいて損はないから、です。
まず、遮熱です。
遮熱とは、太陽から降り注ぐ「輻射熱」を反射させて、建物の内部に熱が入り込まないようにする仕組みのことです。
たとえば、夏の日差しが直接当たる窓ガラス。ここに遮熱ガラスや遮熱フィルムを使うと、赤外線を跳ね返して、室温の上昇を抑えることができます。
なぜ、遮熱が必要なのか?それは、夏場の不快な暑さの大半は、この「太陽熱」のせいだからです。特に西日が強く当たる部屋では、遮熱対策をするだけで、体感温度がかなり変わってきます。
ただし、遮熱は「熱を入れない」ことには強い!ですが、「一度入った熱を閉じ込める」という力はありません。
つまり、冬場にはあまり活躍しません。遮熱の目的はあくまで“外からの熱をカットする”こと、だからです。
つぎに、断熱です。
断熱とは、屋内の温度を保ち、外気の影響を受けにくくする技術や素材のことです。たとえば冬、暖房で温めた空気が外に逃げず、室内がいつまでも暖かい。これが断熱の力です。
断熱材は、外壁・屋根・床・窓など、家のさまざまな場所に使われています。空気をたくさん含んだ素材が多く、熱の移動を遅くするのが特徴です。グラスウール、発泡ウレタン、スタイロフォームなどが有名です。
断熱の本質は「中と外を仕切る力」。だから、夏には外の暑さを防ぎ、冬には中の暖かさを守ります。
ただし、即効性はありません。じんわりと効いてくるイメージです。
結論からいうと、「遮熱」は太陽熱を防ぐ、“外向き”の対策、「断熱」は室内の温度を逃さない、“内向き”の対策です。目的も、使いどころも違います。
比較すると以下のようになります:
| 項目 | 遮熱 | 断熱 |
|---|---|---|
| 主な働き | 外からの熱を防ぐ | 室内の熱を逃がさない |
| 効果的な季節 | 夏 | 冬 |
| 代表的な素材 | 遮熱フィルム、遮熱ガラス | グラスウール、ウレタンなど |
| 対象 | 窓、屋根、外壁 | 壁、屋根、床、窓 |
| 即効性 | 比較的高い | ゆっくり効いてくる |
このように、似ているようで役割は真逆。どちらか一方で十分というよりも、両方のバランスがとても重要です。
多くの方が「断熱すれば夏も涼しい」と思っています。でも、それはちょっと違います。断熱は確かに外気の影響を減らしますが、太陽の強烈な輻射熱まではカットしきれません。だから、断熱だけでは夏は暑いままなんです。
逆に、遮熱フィルムを冬にも貼りっぱなしにしてしまうと、今度はせっかくの太陽熱を室内に取り込めず、暖房効率が落ちるということも起こります。
要するに、遮熱と断熱は「どちらがいい」ではありません。2つを「どう組み合わせるか」が大事です。

遮熱と断熱の違いがわかったところで、次は「どっちを選べばいいの?」ということです。
これは、単純に「どちらが優れているか?」ではありません。なぜなら
によって、正解が違うから、です。
そこで、この章では、目的別・季節別・地域別の使い分けについて、具体的に解説していきます。
夏の暑さがつらい。
その原因の多くは、実は「輻射熱」です。窓から入る日差し、屋根から伝わる熱気。これらがじわじわと室温を上げていきます。このとき活躍するのが遮熱です。
遮熱ガラスや遮熱フィルムは、太陽光のうち赤外線を反射することで、熱の侵入を防ぎます。とくに日当たりが強い南向きや西向きの窓に使うと効果的です。また、屋根裏に遮熱シートを施工すれば、上からの熱気もかなりカットできます。
ただし、遮熱だけでは「こもった熱」を逃がす効果は期待できません。室内の熱気は、換気やエアコンで調整が必要です。遮熱は“外の熱を入れない”ためのものなので、あくまで「暑くなる前の予防」と考えるのが正解です。
冬になると、暖房をつけてもすぐに冷えてしまう。
そんな悩みがあるなら、断熱を見直すべきです。断熱材は、室内の暖かい空気が外へ逃げるのを防ぎます。逆に、外の冷気が中に入り込むのもブロックします。
断熱は家全体に関わるものなので、窓・床・壁・天井のバランスがとても重要です。なかでも窓は熱の出入りが大きく、窓断熱(複層ガラスや内窓など)を強化するだけでも体感温度がかなり変わります。
もちろん、断熱にも限界はあります。たとえば、築年数が古く、隙間風が多い家では、どんな高性能な断熱材を使っても効果は半減してしまいます。断熱を活かすには、気密性とセットで考えることが大切です。
前述した通り、「遮熱か断熱か」ではなく、「両方をうまく組み合わせる」。それが、最も効果的な方法です。
夏は遮熱で熱を入れず、断熱で室温を保ち、冬は断熱で暖かさを守りつつ、必要に応じて太陽熱をうまく取り込む。これが理想的なスタイルです。
たとえば、Low-E複層ガラスという商品があります。これは遮熱性と断熱性を同時に持ったガラスで、季節に応じて熱の出入りをコントロールしてくれます。地域や窓の方角に応じて、「遮熱タイプ」と「断熱タイプ」を選べるのもポイントです。
季節によって入れたい熱、遮りたい熱が違うからこそ、「遮熱と断熱のバランス」が暮らしやすさを左右します。どちらか一方では不十分なケースも多いので、家全体の設計や生活習慣を考慮して、ベストな組み合わせを考えましょう。
じつは、遮熱と断熱の選び方は、住んでいる場所によっても変わってきます。
たとえば、夏が長く厳しい地域(沖縄・九州・関東南部など)では遮熱が必須です。一方、冬の寒さが厳しい北海道や東北などでは、断熱性能を重視しないと快適に暮らせません。
また、都市部のマンションか、郊外の一戸建てかでもニーズは違います。マンションなら日当たりと遮熱を重視すべきですし、戸建てなら屋根断熱や床下断熱まで広くカバーする必要があります。
気候に合った施工をしないと、せっかくの高性能な素材も宝の持ち腐れになります。自分の地域にあった対策を知ることが、失敗しない家づくりの第一歩です。

遮熱や断熱を導入しようと考えたとき、やはり気になるのが費用です。
「いくらかかるの?」「どっちの方がコスパが良い?」と、まずお金のことを気にするのは当然です。特に企業や店舗では、施工費に加え、運用コストや効果の持続性まで見ないと判断できません。
この章では、個人住宅と法人施設の両方の視点から、遮熱・断熱のコストについて本音で解説していきます。
まずはおおよその価格帯を見てみましょう。
※費用は条件によって変動します。以下は参考値です。
| 項目 | 遮熱フィルム | 断熱材(住宅用) |
|---|---|---|
| 材料費 | 4,000〜10,000円/㎡ | 3,000〜8,000円/㎡ |
| 施工費(住宅) | 5,000〜15,000円/㎡(窓面) | 8,000〜20,000円/㎡(壁・床等) |
| 施工費(倉庫・施設) | 要相談(面積・高さに依存) | 高額(大規模断熱は数百万円単位も) |
| 工期の目安 | 数時間〜1日(窓施工のみ) | 2日〜数週間(全面改修の場合) |
遮熱フィルムの最大のメリットは「短時間・小コストで導入できること」です。
特に既存の窓に後から施工できるため、企業の倉庫や工場などでも営業を止めずに工事可能です。
一方、断熱材は建物の構造そのものに手を加える必要があるため、大がかりなリフォームが必要になります。
断熱材は確かに優れた効果があります。
が、施工の手間・費用の面ではハードルが高いのが実情です。その点、遮熱フィルムは「導入のしやすさ」「費用対効果の高さ」で非常にコスパが良い選択肢です。
特に夏場の電気代が悩みの企業や商業施設では、遮熱フィルムを貼るだけで冷房効率が格段にアップします。初期費用はそれほど大きくなくても、毎月の光熱費削減で短期間に元が取れるケースも多いです。
冷暖房が逃げやすい「大きなガラス面」を持つビルや、南向きのショールーム、直射日光が強い物流倉庫などでは、遮熱フィルムの費用対効果は想像以上です。
遮熱フィルムによる冷房費削減効果は、多くの企業が実感しています。
たとえば、平均的な事務所ビルでは年間で10〜30%の冷房費削減につながったという事例もあります。
冷房効率が良くなる理由は、室内温度の上昇を抑えられるから。空調機器の稼働時間や出力が減ることで、自然と光熱費が下がっていくんです。しかも、遮熱フィルムは消費電力ゼロ。メンテナンスもほとんど必要ないため、導入後のランニングコストは極めて低いです。
表で比べてみましょう。
| 項目 | 遮熱フィルム | 断熱材 |
|---|---|---|
| 光熱費削減効果(夏) | ◎(最大30%削減) | △(やや効果あり) |
| 光熱費削減効果(冬) | △(太陽熱を遮る可能性) | ◎(暖房効率アップ) |
| メンテナンス費 | ほぼ不要 | 素材によっては定期点検あり |
| ランニングコスト | 極小 | ほぼゼロ |
このように、夏場に強い遮熱フィルムと、冬に効果的な断熱材は、それぞれに得意分野があります。
「冷房費を削減したい」「設備投資は抑えたい」というニーズには、遮熱フィルムがぴったりです。
企業にとっては、「初期投資」よりも「回収期間」が大事です。
遮熱フィルムの最大の魅力は、比較的安価な初期投資で、すぐに効果が実感できるということ。施工も短時間なので、ビジネスを止めずに対応できるのも大きなメリットです。
一方で、断熱材は「長期的な省エネ設計」として効果を発揮します。建物の基本性能を底上げするものなので、大規模な新築やリノベーションには向いていますが、すぐに回収できるかというと微妙です。
結局のところ、「どう使いたいか」「どのくらいの期間で元を取りたいか」が判断基準になります。とくに既存施設に対して効率よくコストを抑えたいと考えるなら、遮熱フィルムは非常に現実的な選択肢になります。

遮熱と断熱の違いは理解できた。
でも「じゃあ実際、何を使えばいいの?」「どうやって導入するのが正解なの?」という声も多いと思います。特に法人施設の場合、規模が大きくなる分、選び方や施工方法が非常に重要です。
そこで、この章では、目的に応じた商品選びから導入方法まで、実例も交えながらリアルに解説していきます。
もし新築や大規模なリフォームを検討しているなら、窓ガラス自体を断熱・遮熱仕様にするのが一番効果的です。
特におすすめなのが「Low-E(ローイー)ガラス」。これは、ガラスの表面に特殊な金属膜をコーティングし、熱の移動をコントロールする技術です。
Low-Eガラスには主に2種類あります。ひとつは「遮熱タイプ」。これは、夏の暑さを反射してくれるので、南向きや西日の強い窓に最適です。もうひとつは「断熱タイプ」。冬の室内の暖気を逃さず、冷暖房の効率を高めてくれます。
ただし、Low-Eガラスは既存のサッシを交換する必要があり、費用や工期が大きくなる点には注意が必要です。住宅ならリフォームのタイミングで、法人なら新築や大規模改修時に取り入れるのが現実的です。
既存の窓に後から対策したい。
その場合、最も手軽で現実的なのが遮熱フィルムや断熱シートの導入です。特に「遮熱フィルム」は、企業や倉庫での導入実績も多く、短期間で施工でき、費用対効果にも優れています。
遮熱フィルムには、可視光透過率や紫外線カット率など、さまざまな性能指標があります。たとえば、来客の多い店舗であれば「透明感が高く、見た目に違和感のないもの」を、物流倉庫や事務所であれば「反射率が高く、熱遮断効果が強いもの」を選ぶのがポイントです。
企業なら倉庫や工場で使うと光熱費を削減できます。実際に「電気代削減を目的に導入したら、社員の体感温度が下がって生産性もアップした」といった声も多く聞かれます。
また、遮熱フィルムは“貼るだけ”で結果が出やすく、営業を止めずに工事できます。そのため、業務効率を落とさずに環境改善が可能です。
なお、業務用の遮熱フィルムや遮熱シートを検討する際は、遮熱技術に特化した企業に相談するのが一番です。たとえば株式会社エビスでは、倉庫・工場など大型施設での施工実績が豊富です。さらに、現場に合わせた製品提案や技術サポートにも対応しています。まずは、施工の可否やコスト感を含め、情報収集をオススメします。
遮熱・断熱の違いをわけた施工方法は、「自分でやるべきか?業者に依頼すべきか?」で迷う方も多いと思います。
結論から言えば、目的や規模によって使い分けがベストです。
たとえば、自宅の小さな窓だけに遮熱フィルムを貼る程度なら、DIYでも対応可能です。ただし、きれいに貼るにはかなりの技術が必要ですし、失敗すると気泡や歪みが目立ちます。
一方、企業の倉庫やビル、店舗など、大規模な窓や高所作業が発生するケースでは、プロに任せるのが絶対に安全で効率的です。施工業者なら、最適なフィルム選定から、現場の状況に応じた施工計画まで一括対応してくれます。法人案件では「施工後の効果検証」や「定期点検サービス」がセットになっていることも多く、導入後も安心です。
個人宅で遮熱・断熱対策を取り入れるなら、まず注目すべきは「窓」と「天井(屋根裏)」です。窓は熱の出入りが最も激しい場所で、ここを強化するだけでも体感温度は劇的に変わります。
たとえば、西日が強く差し込むリビングには遮熱フィルムを。寒さが気になる北側の部屋には断熱シートや内窓設置を。屋根裏には遮熱シートを施工することで、夏場の2階の暑さがかなり緩和されます。
リフォームの際にどこまで対応するかは、予算と生活スタイル次第。ただし「一部だけでも手を入れる」だけで、住まいの快適性は大きく変わることを、ぜひ体感してほしいです。

「遮熱」と「断熱」の違いは、単なるネーミングではありません。
その背景には、熱の伝わり方の違いや建材に使われている技術の特性があります。
この章では、その“違いの理由”を科学的に、でもわかりやすく解説します。理屈がわかると、商品選びや施工方法に対しても自信を持って判断できるようになりますよ。
まず大前提として、熱には「伝わる仕組み」が3つあります。それが「伝導」「対流」「輻射」です。遮熱と断熱の違いを理解するには、この熱の移動の仕組みを知ることが非常に大切です。
遮熱はこの中の「輻射熱」をブロックする技術です。つまり、太陽光などから出る赤外線のエネルギーを反射させることで、建物内部への熱の侵入を防ぎます。一方、断熱は「伝導」や「対流」に対して有効で、空気を多く含んだ素材で熱の流れを遅くします。
このように、遮熱と断熱は、そもそも戦っている“敵”が違うのです。だからこそ、素材や施工方法もまったく異なります。
建築設計の現場では、遮熱と断熱は「熱環境をコントロールするための別々の手段」として使い分けられます。たとえば、工場や倉庫の屋根には強い日射が当たりやすいため、輻射熱を反射する遮熱シートの施工が効果的です。
一方、住宅では、冬の寒さをしのぐために「断熱材を厚くする」「サッシを高断熱仕様にする」などの対策が重視されます。つまり、建物の用途や立地、構造によって、“どこを守るか”の戦略が違うのです。
遮熱と断熱の違い=“どこを守るか”の戦略が違う
また、空間の使われ方によっても重視すべき要素が変わります。たとえば、冷蔵品を扱う倉庫では断熱が絶対ですが、太陽熱で温まりやすい事務所スペースでは遮熱がカギになります。このように、単なる素材選びだけでなく、現場の使い方まで含めて設計することが求められるのです。
最も効果的なのは、「遮熱」と「断熱」を補完関係として考えることです。夏は遮熱で太陽熱を反射し、断熱で室温をキープ。冬は断熱で暖かさを保ちつつ、場合によっては日射熱を室内に取り入れる設計も必要です。
こうした最適解を導くには、やはり専門知識を持ったパートナーと連携することが大切です。
専門業社は、現場の温度分布や冷暖房機器との相性まで見据えたアプローチをします。結果的に、最終的なコスト削減と快適性の両立につながります。
近年では、省エネやカーボンニュートラルの流れもあり、遮熱・断熱技術はますます進化しています。たとえば、反射性と透光性を両立した高性能フィルムや、自己修復機能をもつ断熱材など、建材そのものの性能が上がってきています。
また、IoTと連携した「温度モニタリングシステム」などを活用すれば、リアルタイムで遮熱・断熱の効果を可視化することも可能に。これからの時代は、ただ“施工して終わり”ではなく、結果が見える断熱・遮熱が求められるのかもしれません。
こうした最新技術も、専門企業を通じて早くから取り入れることができるので、興味がある方はまず情報収集からはじめてみてはいかがでしょうか。

遮熱と断熱の違いをお伝えしました。
この2つは、それぞれに得意分野があります。そのため、どちらか一方だけでは快適な環境づくりは難しいのが実情です。
つまり、場所・季節・目的に応じてうまく組み合わせることが重要。とくに企業や倉庫などでは、効果だけでなくコストや施工のしやすさも重要な判断基準になります。
遮熱フィルムや断熱材の導入を検討する際は、現場の状況に応じた適切な提案ができる専門業者との連携が鍵です。
少しの工夫が、大きな省エネ・快適性につながります。
今回も最後まで読んで頂きありがとうございました。
ご相談・ご質問等ございましたら
お気軽にお問い合わせください。